相続で残された家は、遺族にとって思い出が詰まった場所である一方、現実的には「管理の負担」や「処分費用」という大きな問題を抱えています。
今回ご相談いただいたのは、昭和57年築の木造住宅。空き家となり、中には長年の荷物がそのまま残っている状態でした。
相続物件に潜む負担とリスク
まず直面するのが 残置物処分費用 です。
一般の方が業者に依頼すると、100万円前後 はかかります。これだけでも相続人にとっては重い負担です。
さらに、この物件は 接道義務を満たしていない可能性 がありました。
- 道路判定を受けていない
- 道路は法人・個人所有
- 掘削許可や通行同意が必要
このような条件では再建築不可となる可能性が高く、土地としての評価が難しい状況でした。
建物の可能性と相続人への提案
建物自体は構造がしっかりしており、傾きや雨漏れもなく、駐車スペースも1台分は確保可能。
私は相続人の方に、
「もしご自身でリフォームして賃貸にすれば、毎月家賃収入を得る選択肢もあります」
と正直にご提案しました。
しかし、相続人の方からは、
- プロではないのでリフォームや賃貸経営は難しい
- 契約不適合責任やトラブルを背負いたくない
- 出来るだけスムーズに処分したい
というご意向を伺いました。
そのため、「直接買取」という流れになったのです。
相続物件の処分方法 ― 3つの選択肢比較
相続物件をどう処分するかには、大きく分けて3つの選択肢があります。
| 処分方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ① 自分でリフォームして賃貸化 | ・毎月の家賃収入を得られる ・資産価値を維持できる | ・残置物処分+リフォームで300〜400万円以上必要 ・入居者対応や修繕の負担 ・素人にはハードルが高い |
| ② 業者(投資家)へ売却 | ・早期現金化が可能 ・契約不適合責任を回避できる ・トラブルリスクを避けられる | ・市場相場より安い価格での売却になる |
| ③ そのまま放置 | ・初期費用ゼロ | ・固定資産税・管理費がかかり続ける ・老朽化による解体費用リスク ・近隣トラブルや資産価値低下 |
今回のケースでは、相続人の方が「リフォームや賃貸経営は難しい」「責任を背負いたくない」というお考えでしたので、② 業者への直接売却 が最適解となりました。
投資家目線のシミュレーション
私自身が買い取って賃貸化する場合の数字を整理しました。
| 項目 | シナリオ①(一般処分費用) | シナリオ②(費用圧縮後) |
|---|---|---|
| 想定家賃 | 6万円/月 | 6万円/月 |
| 年間収入 | 72万円 | 72万円 |
| 5年間収入 | 360万円 | 360万円 |
| 残置物処分 | 100万円 | 50万円 |
| リフォーム費用 | 250万円 | 250万円 |
| 購入費用 | 60万円 | 60万円 |
| 総投資額 | 410万円 | 360万円 |
| 利回り(表面) | 約17.5% | 約20% |
※私のネットワークを活用すれば残置物処分費を抑えられるため、20%利回りのスキームが実現可能です。
出口戦略
投資家としては、2つの出口戦略を描いています。
① 短期キャピタル戦略
- 利回り20%で仕込み
- 賃貸化・入居付け後にオーナーチェンジ売却
- 利回り15%程度に落としても十分に売却可能
② 長期インカム戦略
- 賃貸経営を継続して安定した家賃収入を得る
- 道路判定や通行同意を並行して進める
- 将来的に「再建築可能物件」に昇格できれば、資産価値は大幅アップ
まとめ
相続物件は「残置物処分費用100万円」「接道義務リスク」といった課題を抱えることが多く、一般の方にとっては大きな負担です。
しかし投資家の視点で数字を逆算し、出口戦略を描けば、総投資360〜410万円 → 年収72万円 → 利回り17〜20% という高利回り案件に仕立てることが可能です。
相続人にとっては「負担を軽くして早期に処分できる」メリットがあり、投資家にとっては「高利回りを狙える」メリットがある。
双方にとって納得のいく形が実現できた事例だと感じています。
不動産投資は「買った瞬間に勝負が決まる」と言われます。
リスクを正しく把握し、利回りと出口を設計することが、安定的な資産形成の王道です。
相続物件でお困りの方へ
もしこの記事を読まれている方の中に、
- 相続で使わなくなった家がある
- 農地や再建築できない土地をどうすればいいか分からない
- 処分も売却も進まずに困っている
という状況にある方がいらっしゃれば、ぜひ一度ご相談ください。
状況に合わせた最適な方法を一緒に考え、無理のない形で解決に向けて動ければと思います。

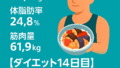
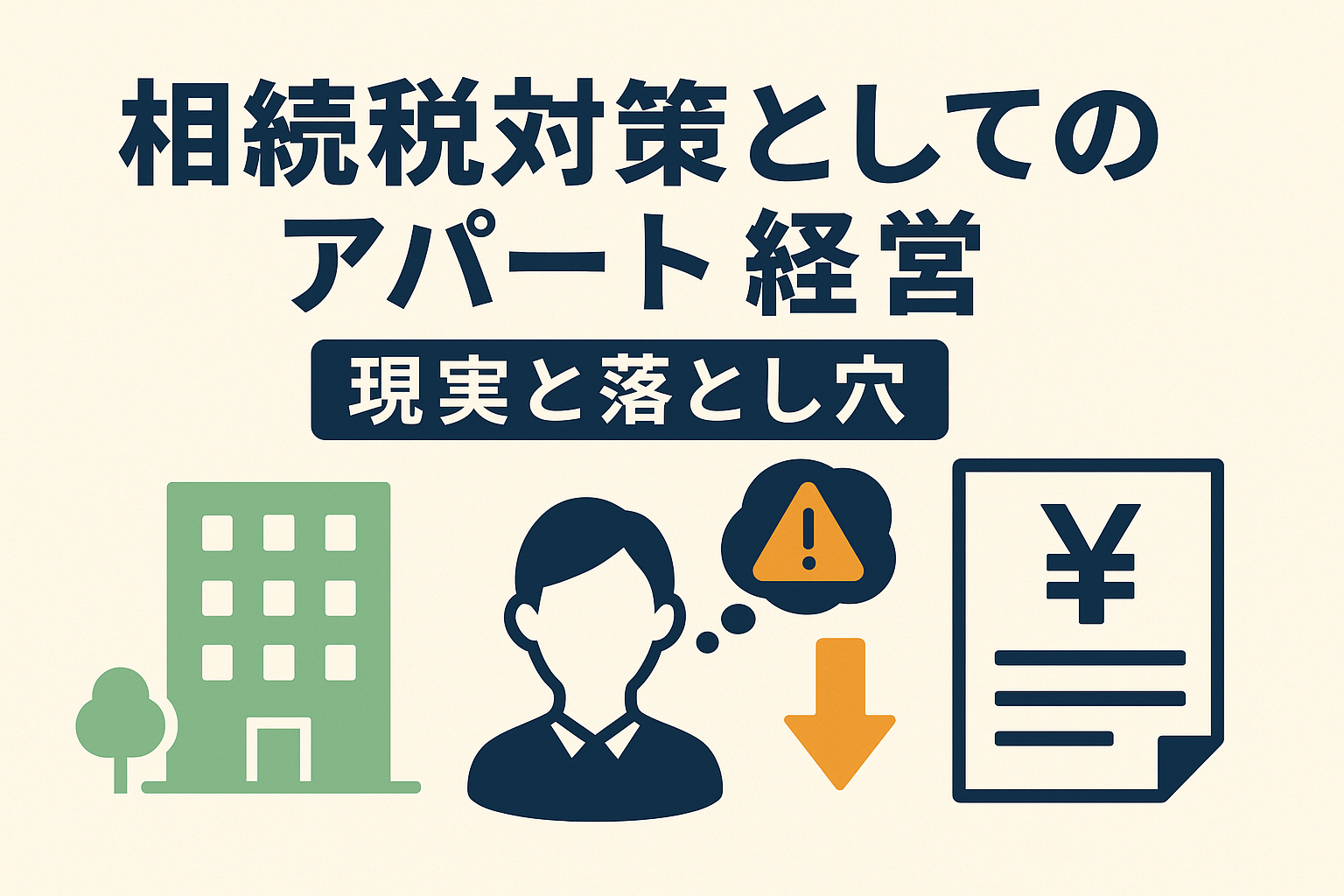
コメント